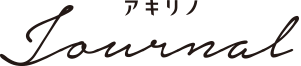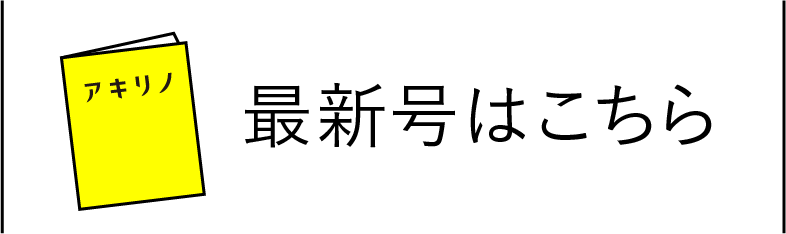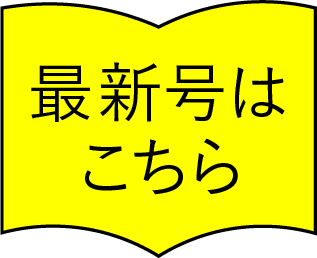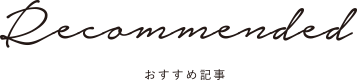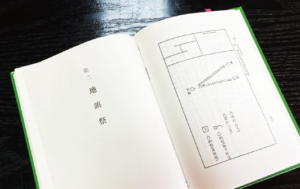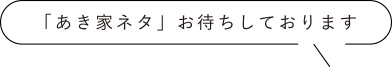古民家の学校 vol.15「大工」について詳しく知りたい
木造の建築物を建てたり、修理を行う職人「大工」。昔は木を扱う職を右官、土に関わる職を左官と呼んでいたという説もあります。今回は大工について伝統技術を活かした設計・施工を手掛ける松尾工務店の松尾正崇さんにお話を聞きました。

*****
教えてくれたのは
伝統建築技能者/松尾正崇(まさたか)さん
坂出市出身。1946年創業「松尾工務店」大工・建築士。2代目である父の背中をみて、子どもの頃から大工を目指す。
伝統構法を活かした家の建築や文化財の修復に従事。
Q:日本古来から伝わる伝統構法とはどのような建築技術ですか?
A:木の特性を活かし、木と木を組み上げて家を建てる工法です。金物をあまり使わず、継手・仕口※によって大きな木を柱と梁として組み合わせていきます。大工はまず木を見ることから始まります。山の北側に生えた木、南側に生えた木など木が育った場所により、性質や強さはそれぞれ違います。切った後も木は生きています。出来るだけ育った環境と同じ環境で使ってあげると、木本来の力を発揮すると思います。
※木材を継ぐ方法

木そのままの形を活かし、組み上げた梁

”いろは”と漢数字が目印
Q:今でも使われている大工道具には、どのようなものがありますか?
A:大工道具にも三種の神器があります。木材に直線を引く「墨ツボ」、材木などの長さや直角を図るちょうな
「指金」、木を成形する「釿(ちょうな)」です。これは木を伐りだして最初に使う道具として、お正月の三が日に大工の作業所に飾る風習があります。その他「鉋(かんな)」や、木材を切断し継手を仕上げる「鑿(のみ)」は作業する場所に合わせて大きさや形が違うものを使います。よい仕事をするためには道具の手入れも大切ですね。

ちょうなで木を削りながら形を整える

作業所の正月飾り
松尾工務店さんお話ありがとうございました。