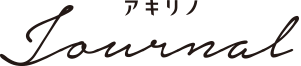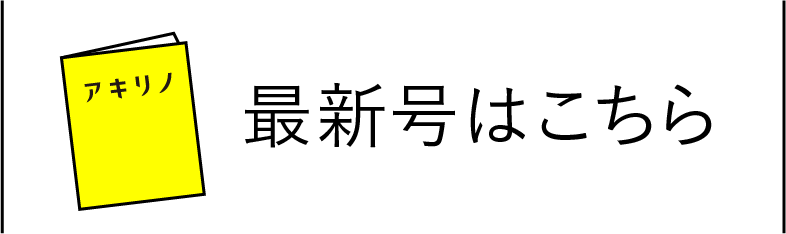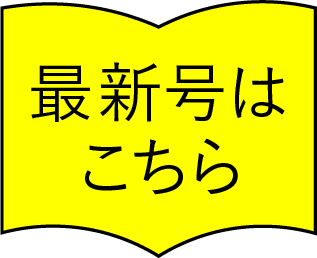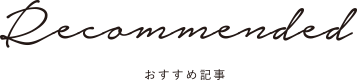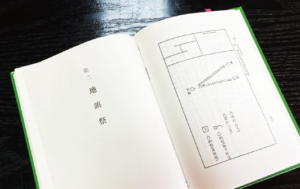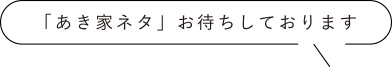古民家の学校 vol.14「左官」について詳しく知りたい
縄文時代の竪穴式住居の土塀作りがルーツという説もある「左官」。安土桃山時代には茶室の建築において左官が活躍していたといわれています。まさに日本の歴史とともに培われてきた左官の技術。今回は左官について石田均さんにお話をお聞きしました。

*****
教えてくれたのは
一級左官技能士/石田均さん
さぬき市出身。高校卒業後、石田左官工業に入社し、父と共に文化財修復に携わる。
全国文化財壁技術保存会理事であり、若い後継者育成にも力を注いでいる。左官(日本壁)技能者。
Q:文化財の修復はどのような工程で行っているのですか?
A:古い建築物は長い歴史を経て、さまざまな人の手で修復が加えられてきました。土壁で形成された建物もその時代の修理工事で塗り替えられています。江戸時代では聚楽(じゅらく)などの上塗り材を使用していたようです。
私たちはその背景を探りながら解体を行い、どの時代の壁に戻すのかを文化庁の担当の方たちと相談して修復していきます。修復させる時代が決まると元の素材を活用したり、近い素材を取り寄せて復元していくのです。

県内外の重要文化財の修復を手掛けた
Q:日本と海外では道具や工法などの違いはありますか?
A:西洋の工法は見たことがないのでわかりませんが、中国に行ったときは鏝(こて)などの道具はほとんど同じでした。所々土レンガを使用していたかな。ブータンでは仮囲いをして土を叩き固めて壁を作っているのを見たと聞きました。この工法は日本で昔、土塀造りで行われていました。コンクリートにも引けを取らない強度の土塀を今の時代作ろうとすると、人手と時間そして費用も相当かかるでしょうね。

蔵の壁を作る工法を再現。団子状にした土を手で木舞壁(こまいかべ)※につけていく ※竹を縦横に組んだ下地
石田左官工業さんお話ありがとうございました。