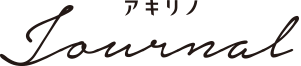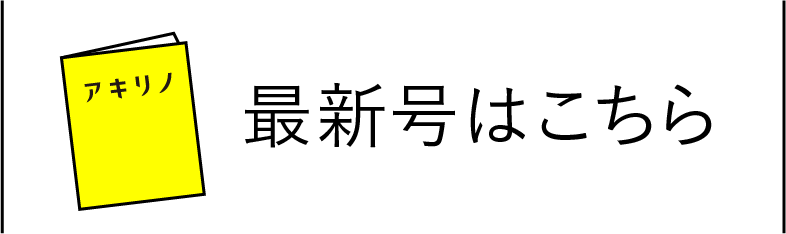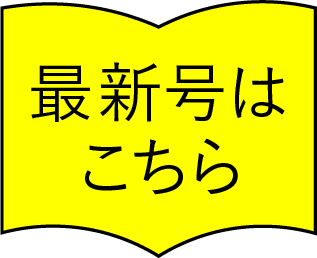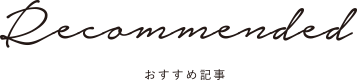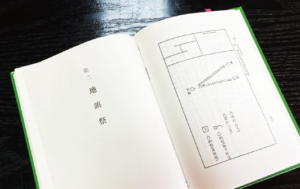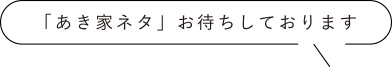古民家の学校 vol.7 「欄間彫刻師」について詳しく知りたい
天井と鴨居(かもい)との間にある欄間は、主に室内の採光や風通しをよくするためのもの。木目を活かした繊細で格調高い欄間彫刻は、日本建築の室内装飾として発展してきました。桃山時代から江戸時代にかけて盛んになり、香川県では、高松藩主・松平頼重の時代に伝わったとされています。欄間彫刻の香川県伝統工芸士である朝倉準一さんにお話を聞いてきました。

*****
教えてくれたのは
彫刻師/朝倉準一さん
1868年に宮大工として創業した「朝倉彫刻店」の6代目。1998年から家業の彫刻業に進み、 28歳の時に父の後を引き継ぐ。
2019年には欄間彫刻で香川県伝統工芸士に認定
Q:欄間彫刻の魅力と彫刻師としてのやりがいを教えてください。
A:欄間彫刻の魅力は木目を活かした美しさでしょう。もちろんすべて木の状態も違うから、同じ絵面であっても同じものは一つもない。今の建築では欄間自体があまり使われないので、欄間彫刻の仕事は少ないですが、建具と違ってほとんど傷むことがないので、ほぼ永続的に残っています。寺社仏閣や太鼓台、街の中の看板や柱に、僕や父の作ったものが残っていることが、彫刻師としてのやりがいですね。

父である理さんと二人で彫った思い出の作品。作業場に飾られている
Q:欄間彫刻で気をつけていることは何ですか。
A:設置する場所を事前に確認することですね。なぜかというと、欄間というのは真正面で見るわけではないので、どのくらい高い場所に設置するのか、位置関係や視線の角度を考えて彫っていきます。彫る素材選びも重要ですね。透かし部分の木を抜くと、大抵歪みが出ます。うねりがあまりに大きいと木の選別からやり直しになるので、そうならないようにできるだけ穏やかな木を選びます。施主から伐採が停止された仕入れの難しい木を注文された時は、探すのだけで4年近くかかったこともあります。

作業場の風景。机に並べられているのはふだん使いの彫刻刀。まだ引き出しにはたくさん
Q:今後の展望を教えてください。
A:香川県の欄間彫刻の伝統工芸士は僕を入れて6人。一番若い僕が亡くなれば、香川県から欄間彫刻というジャンルも消滅します。後継者ができたとしても、欄間自体の需要が少ないので存続が難しいかもしれません。それは僕が父から稼業を受け継いだ時から感じていたので、箸やボールペンなどの製作も始めました。今ではコレクターから「これで作って欲しい」と、世界中の木で依頼があるので、削った木は250種くらいあります。でもやっぱり彫るのが好きなので、いつか大きな木を彫ってみたいですね。

さまざまな種類の木で、箸やボールペンを作成してくれる

朝倉彫刻店さんお話ありがとうございました。